お客さまが頑張っているから、
翻訳者も、チェッカーも、
プロジェクトマネージャーの私も、
もっと頑張らなきゃって、
刺激をもらいます。
この言葉を受けとる人は、
どんな人だろう?
暮らしがある。切実な現実もある。
翻訳の役割を、改めて考える。
言葉は生き物。
業界のトレンドや常識も
変わり続けるからこそ、
「今」を、徹底して調べる。
そこからすべてが始まります。
企業・官公庁から、
美術館や寺社仏閣まで。
ニーズ整理、プランニング。
時間は有限。
だから、迅速に。
10カ国語でデザインする場合
適切なレイアウトとは?
ふさわしいフォントとは?
最後のランナーとして
伝わるデザインを心がけます。
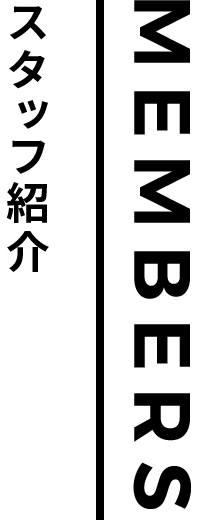
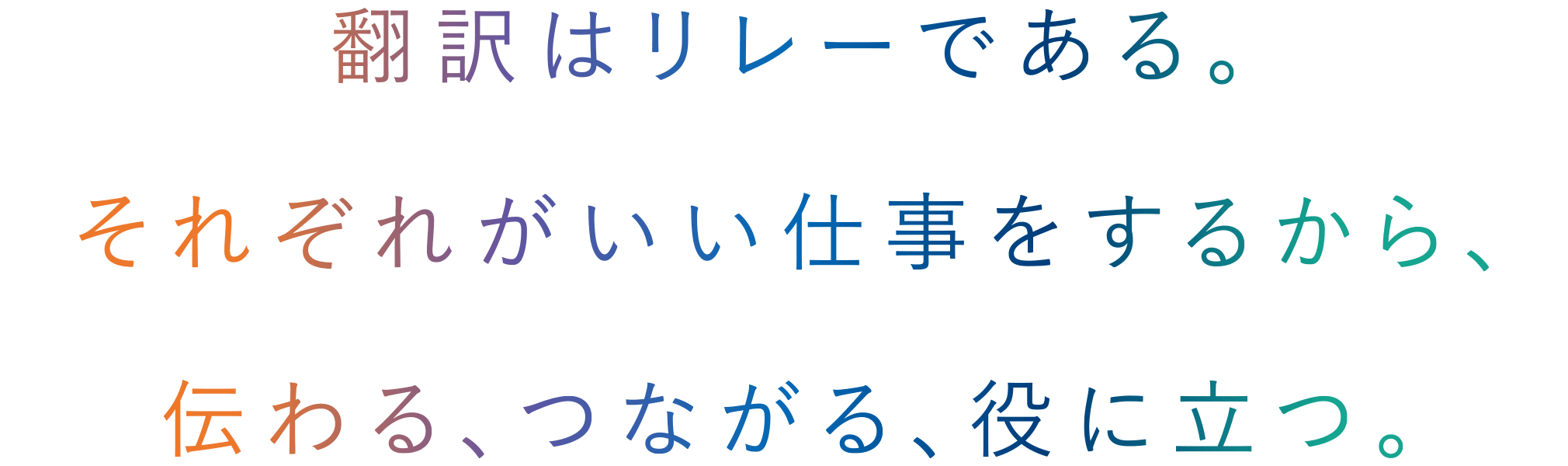
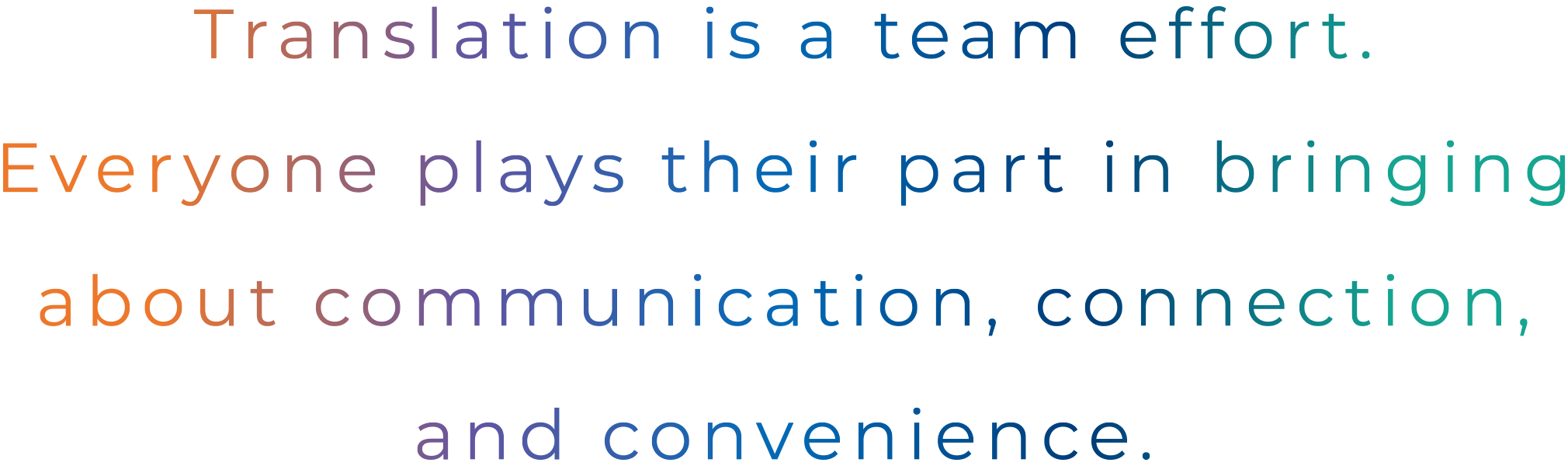
フロントに立つ営業。アサイン・発注・プロセス管理を行うプロジェクトマネージャー。翻訳を行う翻訳者。翻訳の品質をチェックするチェッカー。翻訳をデザインに落とし込むDTPオペレーター。一人ひとりが持ち場でいい仕事をすること。リレーをつなぎます。

お客さまが頑張っているから、
翻訳者も、チェッカーも、
プロジェクトマネージャーの私も、
もっと頑張らなきゃって、
刺激をもらいます。
プロジェクトマネージャー 麻生佳澄

この言葉を受けとる人は、
どんな人だろう?
暮らしがある。切実な現実もある。
翻訳の役割を、改めて考える。
多言語事業部長 上野江理

言葉は生き物。
業界のトレンドや常識も
変わり続けるからこそ、
「今」を、徹底して調べる。
そこからすべてが始まります。
翻訳者・チェッカー 益本愛子

企業・官公庁から、
美術館や寺社仏閣まで。
ニーズ整理、プランニング。
時間は有限。
だから、迅速に。
営業 荒川恵里

10カ国語でデザインする場合
適切なレイアウトとは?
ふさわしいフォントとは?
最後のランナーとして
伝わるデザインを心がけます。
多言語DTPスペシャリスト 近藤令子
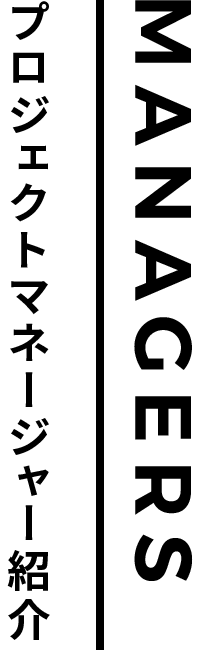
国籍も、性格も、得意分野も人それぞれ。いろんなタイプのプロジェクトマネージャーが在籍しています。ご相談いただいた案件の分野・領域・性質に合わせて最適なプロジェクトマネージャーをアサインいたします。ぜひお気軽に相談くださいませ。