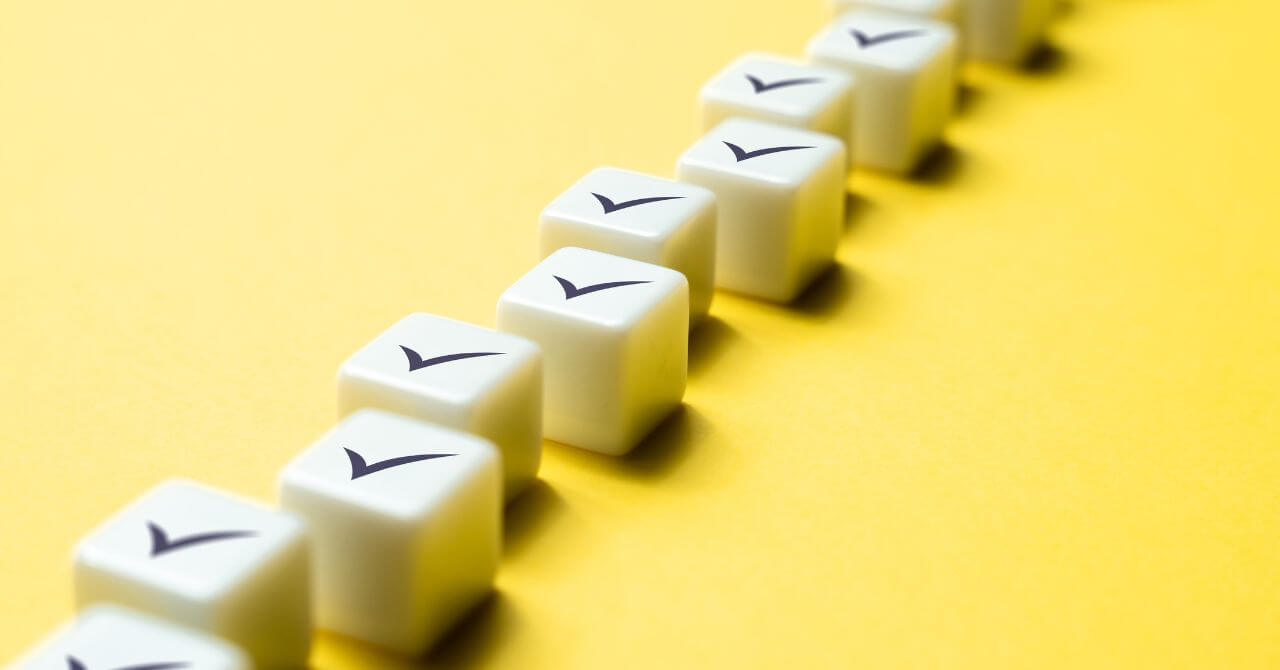- 2025.05.12更新
- 翻訳外注ノウハウ
【翻訳を社内で対応すべきか?】内製の5つのメリットとデメリットを徹底比較

契約書やプレゼン資料、製品マニュアルなど、翻訳が必要となるシーンはある日突然やってきます。そのときにまず検討すべきは、「社内で翻訳(=内製)するか」「外部に依頼(=外注)するか」の選択です。
本コラムでは、翻訳を内製する場合の代表的なメリットとデメリットを5つずつ整理し、実際に翻訳対応が必要になった際に役立つ判断材料としてご紹介します。
翻訳を内製する5つのメリット・デメリット
| 観点 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| コスト | 外注コスト(翻訳料金・再翻訳・検収・再手配など)を抑えられる | 翻訳にかかる「時間コスト」は増える可能性がある |
| セキュリティ | 原稿を社外に出さず、情報漏洩のリスクを低減できる | 無料の自動翻訳ツールの利用は逆にセキュリティを損なう恐れも |
| 情報共有 | 翻訳の目的や社内用語などの共有が不要、手間が省ける | 外注と違って客観的視点の翻訳品質チェックがしにくい |
| ノウハウ蓄積 | 翻訳辞書や用語集を蓄積し、品質の安定化・効率化が図れる | 業界標準や最新トレンドからは取り残されるリスクがある |
| 意識改革 | 翻訳に向き合うことで、異文化理解・国際感覚が養われる | 翻訳精度や成果に対する過信が起きやすくなる恐れも |
翻訳を内製する際の注意点
-
人材の確保:外国語スキルだけでなく、翻訳のスキルや背景知識も必要です。
-
品質管理:翻訳の成果がビジネスの信頼性に直結するケースも多く、誤訳のリスクには十分な注意が必要です。
-
本業とのバランス:翻訳作業が他の業務に支障をきたすことのないよう、スケジュールとリソースの調整が必要です。
最適解は「目的に応じた使い分け」
翻訳の内製と外注、どちらが優れているというものではありません。重要なのは、「翻訳の目的」と「期待する成果」に応じて、最適な手段を選ぶことです。
迷ったときは、複数の翻訳会社に相談して比較検討してみましょう。対応の丁寧さや提案内容から、信頼できるパートナーを見つけるヒントが得られるはずです。
まとめ
翻訳の内製には、コスト・セキュリティ・情報共有面での大きな利点があります。一方で、時間や品質確保、社内リソースへの影響といった課題も無視できません。
翻訳する文書の重要性や目的、社内のリソース状況を踏まえ、内製と外注を上手に使い分けることが、ビジネス成功への第一歩となります。
当社では、英語をはじめとする世界85言語に対応し、契約書・マニュアル・プレゼン資料・ウェブサイト・アプリなど、あらゆるビジネス文書のプロ翻訳を提供しています。
高品質な翻訳をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
外国語対応でお困りですか? どうぞお気軽にお問い合わせください。
無料ご相談・お問い合わせフォーム関連記事