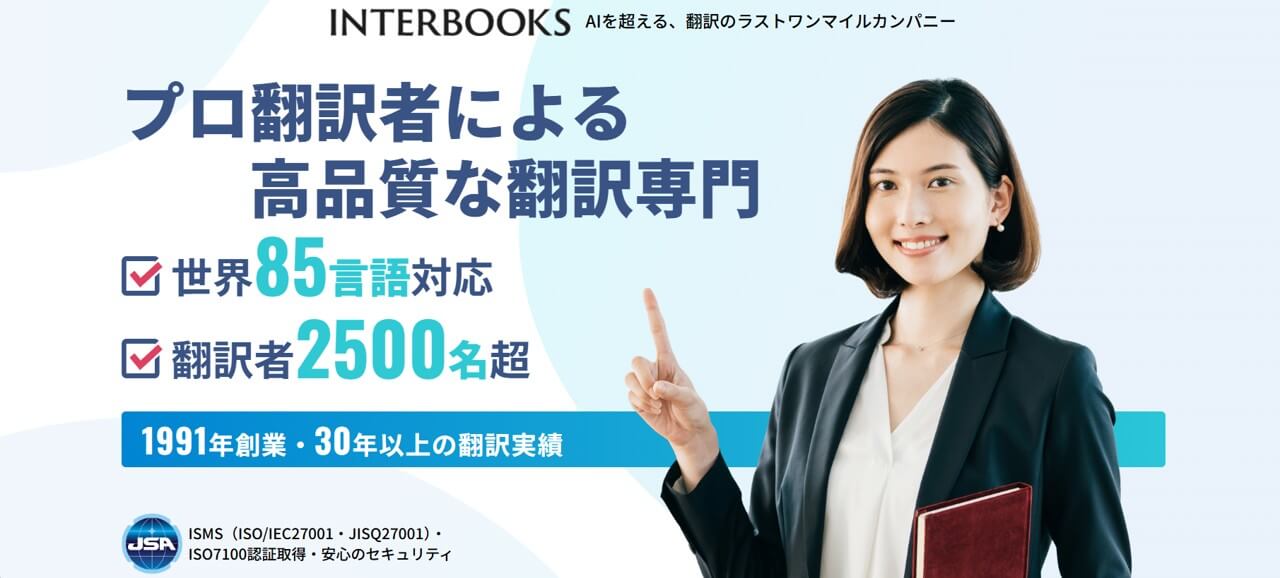- 2025.10.29更新
- 翻訳外注ノウハウ
【プロが解説!】自動翻訳・AI翻訳の正しい使い方

最近では、DeepL、Google 翻訳、ChatGPTなど、機械・AI翻訳技術の進化が著しく、翻訳の初期段階において「まずAIで翻訳してみる」という選択肢が広まっています。一方で、単に「自動翻訳をかけただけ」では、専門用語の誤訳・文脈ずれ・ブランドトーンの喪失などが起きやすく、結果的に信頼性を損なうリスクもあります。
だからこそ、最後には必ず人手による校正・編集・品質管理を組み込むことが、自動翻訳・AI翻訳時代における正しい使い方と言えるでしょう。以下では、自動翻訳・AI翻訳のメリットと限界、人手校正の必要性、自社(インターブックス)での校正体制、そして依頼者が確認すべきポイントを5つの観点で詳しく解説します。
自動翻訳・AI翻訳の現状と活用メリット
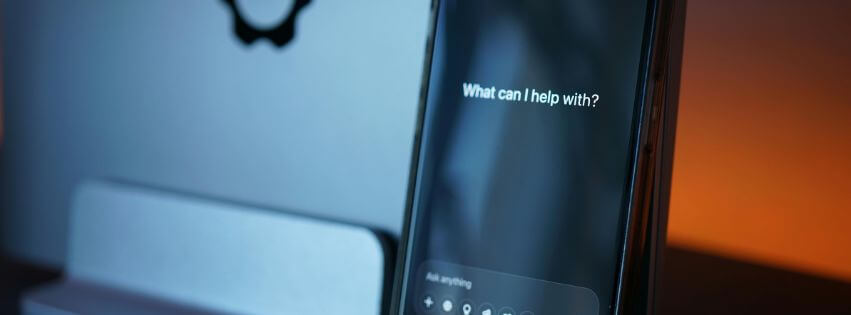
翻訳ツールの進化
近年、ニューラル機械翻訳(NMT)をはじめとするAI翻訳エンジンは、翻訳精度・自然さともに飛躍的に向上しています。例えば AI 翻訳を通じて「初稿生成→人手校正」のワークフローを構築する企業も増えています。
活用できる場面
- 定型【FAQ/マニュアル一部】などでコスト削減を図る場面
- 更新頻度が高く、短納期を要するコンテンツの“仮翻訳”として
- 多言語化を検討中の初期導入段階で、コストとスピードを重視する用途
メリットまとめ
- 翻訳初稿を高速に生成できる(スループット向上)
- コストを抑えた翻訳運用が可能
- 多言語対応のハードルを下げ、展開スピードを早められる
これらは翻訳プロジェクトをスケールさせる上で有効な武器となりえます。
自動翻訳・AI翻訳の限界とリスク

文脈・ニュアンスのズレ
機械翻訳は文節や単語の意味変換を得意としますが、長文の文脈や段落構造、暗示的な意味・ブランドメッセージを捉えるのはまだ万能ではありません。
専門用語・業界知識の不足
技術・法律・医療・IR資料など専門性の高い文書では、訳語選定や業界慣用語の扱いに誤りが出ることがあります。
文化・表現・語用論の課題
海外顧客向け、ブランド向け、マーケティング向け翻訳では、文化的背景・ターゲット読者・表現トーンが重要ですが、自動翻訳だけでは「直訳=伝わらない」事態に陥ることがあります。
用語・表記の統一性が保てない
複数回翻訳・複数言語に展開する場合、訳語のブレ・用語統一の欠如が起きやすく、ブランド一貫性を損ねる恐れがあります。
データセキュリティ・品質保証の課題
クラウド型機械翻訳や無調整のエンジン使用では、機密情報流出・誤訳放置のリスクが存在します。
これらの理由から、「自動翻訳だけに任せる」ことは慎重を要するのです。
人手翻訳・校正の役割と、なぜ“最後に人”が必要なのか
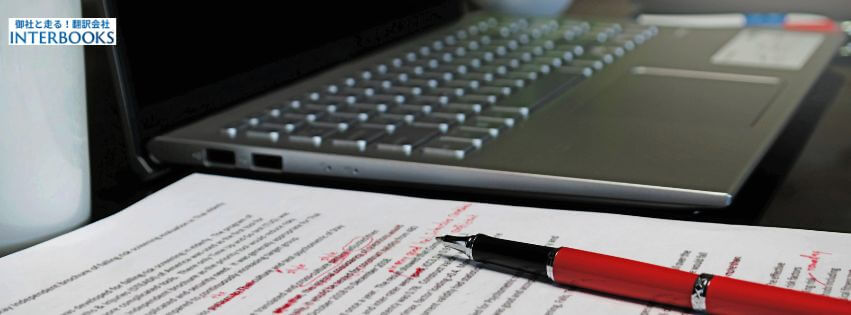
校正・ネイティブチェックの重要性
例えば、インターブックスの「多言語校正センター」では、AI翻訳した文章でも“ネイティブチェック”や“バイリンガル対訳チェック”を行っています。校正では「訳文として自然か」「専門用語・表記仕様は適切か」「ブランドトーンは維持されているか」を確認します。
品質保証体制
インターブックスでは、翻訳者・校正者・編集チームが連携し、ISO 17100(翻訳品質)・ISMS(情報セキュリティ)等の認証取得によるチェック体制を実装しています。
“人ならでは”の強み
- ターゲット読者に響く表現を“選択”できる
- 文化背景・トーン・文脈を踏まえて微調整が可能
- 複数言語・多媒体展開時の一貫性を担保できる
つまり、自動翻訳で出力された“骨格”を、“肉付け”し、安心・信頼できる“商品”に仕上げるのが人手翻訳・校正の役割です。
自動翻訳・AI翻訳を“正しく使う”ための5+αのポイント

以下は、企業や翻訳発注者が「自動翻訳・AI翻訳を活用しながら、品質を保つ」ために押さえておくべきポイントです。
ポイント1:用途・目的を明確に区分する
すべての文書を同列に扱うのではなく、例えば「社内参考資料」「社外対外文書」「ブランド訴求資料」など、用途ごとに翻訳方式を切り分けましょう。
例:社内用ならAI初稿+軽校正、対外公開資料なら人手翻訳+校正というように。
ポイント2:用語集・スタイルガイド・ブランドトーンを整備
AI翻訳が初稿を生成する段階で、あらかじめ用語集・過去訳・ブランド用語を整備しておくと、訳語のブレを抑えられます。インターブックスでは用語統一による品質管理を支援しています。
ポイント3:ポストエディット(人手校正)プロセスを必須とする
AI翻訳を使っても“人のチェック=校正”を省略してはいけません。ネイティブチェック・対訳チェックなど、校正工程を設けることで、訳漏れ・誤訳・言い回しの不自然さを防ぎます。
ポイント4:品質指標・レビュー体制を設ける
校正だけでなく、「読みやすさ」「用語統一」「ブランド語調」「読者の理解度」などを評価する指標を設定し、レビューサイクルを回しましょう。
ポイント5:運用ワークフローを定義する
「プレエディット(原文をAI翻訳向けに整える)→AI翻訳→ポストエディット→校正→納品」というシームレスなワークフローを設計し、担当者・スケジュール・チェックポイントを明確にしておくことが重要です。
ポイント6:更新・再利用性を意識する
AI翻訳を使って生成した訳文や校正履歴を、翻訳メモリ(TM)として蓄積し、次回以降のコスト削減・品質安定化に活かしましょう。
ポイント7:セキュリティ・機密性に配慮する
クラウド型のAI翻訳では、入力データが外部サーバーに保存されるケースがあるため、機密性の高い文書ではオンプレミス・人手翻訳併用を検討する必要があります。
インターブックスが提供する“自動翻訳+校正”ソリューション

多言語校正センターの紹介
インターブックスでは、AI翻訳利用後の“ラストワンマイル”として「多言語校正センター」を提供しており、翻訳初稿のチェック・校正を専門サービスとして展開しています。
ワンストップ体制:翻訳+編集+校正+DTP
翻訳だけでなく、レイアウト・DTP・多言語展開にも対応可能な体制を有しており、自動翻訳を起点とした場合でも、最終品質までワンストップで支援できます。
導入実績と信頼性
創業30年以上、世界85言語以上対応、ISO 17100/ISO 27001(ISMS)認証取得など、品質・機密対応の実績があります。
運用提案:AI+人手ハイブリッドモデル
「AIで初稿を作成→人手校正・ネイティブチェック→多言語DTP対応」というハイブリッドモデルを提案し、コスト・スピード・品質の三立を図ります。
ご相談・見積りプロセス
無料相談・お見積り対応など、導入の段階から丁寧に支援しています(多言語校正センター見積り最短30分)
まとめ:自動翻訳・AI翻訳の“正しい使い方”を徹底しよう

自動翻訳・AI翻訳は、翻訳業務における選択肢として確実にその存在感を増しています。しかし、“自動翻訳だけ”では安心・適切な翻訳にはならないという認識が不可欠です。人手による校正・編集・品質保証を最後まで担保することこそが、翻訳品質・ブランド価値・国際対応力を守る鍵です。
以下、押さえておきたい主な観点を改めて整理します:
- 文書の用途・目的を明確にし、翻訳方式(AI初稿/人手翻訳)を使い分ける
- 用語集・スタイルガイド・ブランドトーンを事前に整備し、統一性を確保
- AI翻訳後には必ずポストエディット(人手校正)を挟む
- 品質指標・レビュー体制・運用ワークフローを設け、運用可能な体制を構築
- 翻訳メモリ・更新運用・データ蓄積を活用して、継続的に品質と効率を向上
- セキュリティ・機密性・ブランド保護を視野に入れ、クラウド・AIの導入を慎重に進める
株式会社インターブックスは、自動翻訳・AI翻訳を活用する際の「最後の仕上げ=人手校正・品質保証」をワンストップで支援できる体制を整えています。AIを“活かしながら”、人の力を“省かずに”翻訳品質を守る。このアプローチこそが、現代のグローバル情報発信において重要です。
翻訳・多言語対応・校正に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
「インターブックスの多言語校正サービス」について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
「MTPE(機械翻訳ポストエディット)作業のポイント」について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
外国語対応でお困りですか? どうぞお気軽にお問い合わせください。
無料ご相談・お問い合わせフォーム関連記事

【翻訳を依頼する前に必ず伝えるべき5つの情報とは?】スムーズな発注のためのチェックリスト
- 翻訳外注ノウハウ
- 2024.02.12

【翻訳方法はどう選ぶ?】目的別に賢く使い分ける4つの翻訳手法とその選び方ガイド
- 翻訳外注ノウハウ
- 2023.10.30

【初めての翻訳外注で失敗しないための完全ガイド】発注から納品後までの全手順を解説
- 翻訳外注ノウハウ
- 2024.01.08

【翻訳外注を成功に導く「5W1H+α」】徹底解説:伝えるべき7つの情報とは?
- 翻訳外注ノウハウ
- 2024.03.11
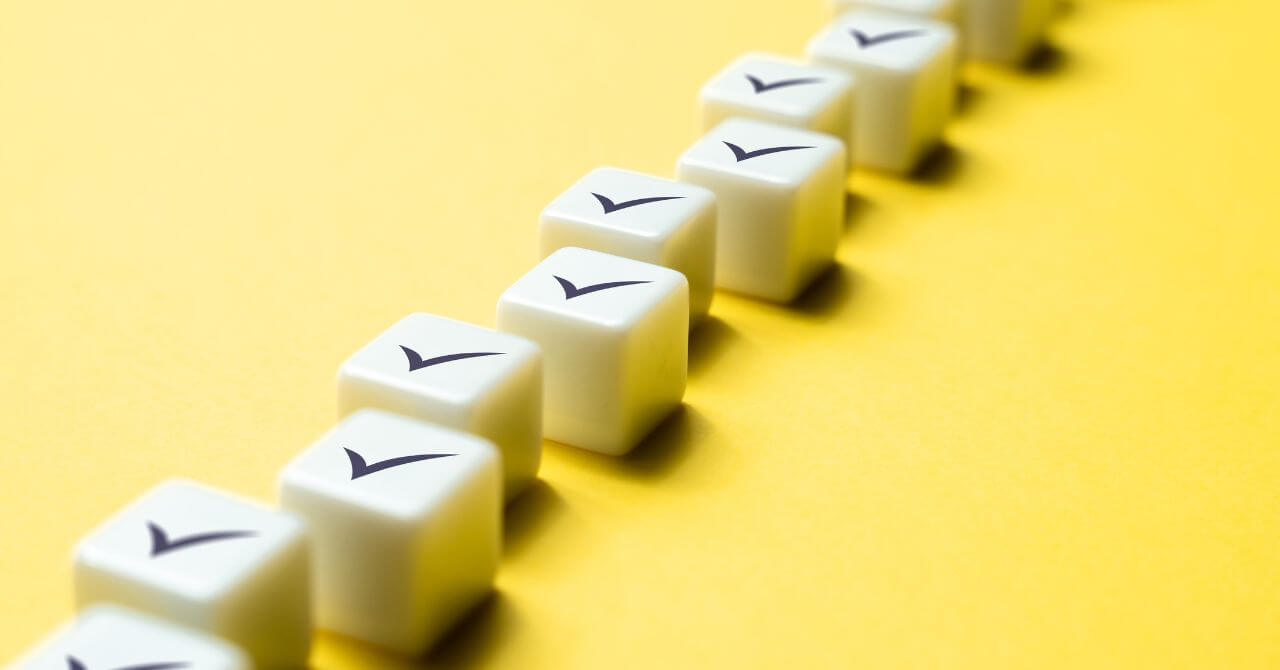
【完全保存版】翻訳を外注するときに絶対にすべき10のこと
- 翻訳外注ノウハウ
- 2024.03.18
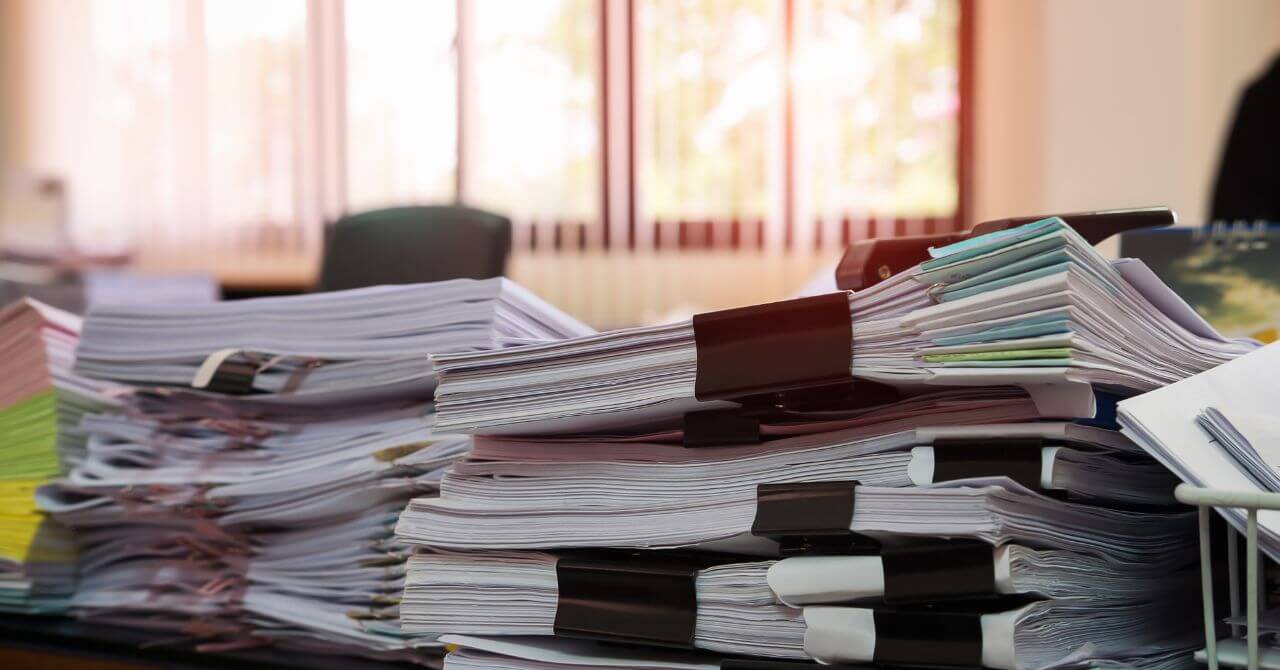
【ビジネス文書の翻訳はなぜ翻訳会社に任せるべきか】外注すべき5つの明確な理由
- 翻訳外注ノウハウ
- 2024.07.08