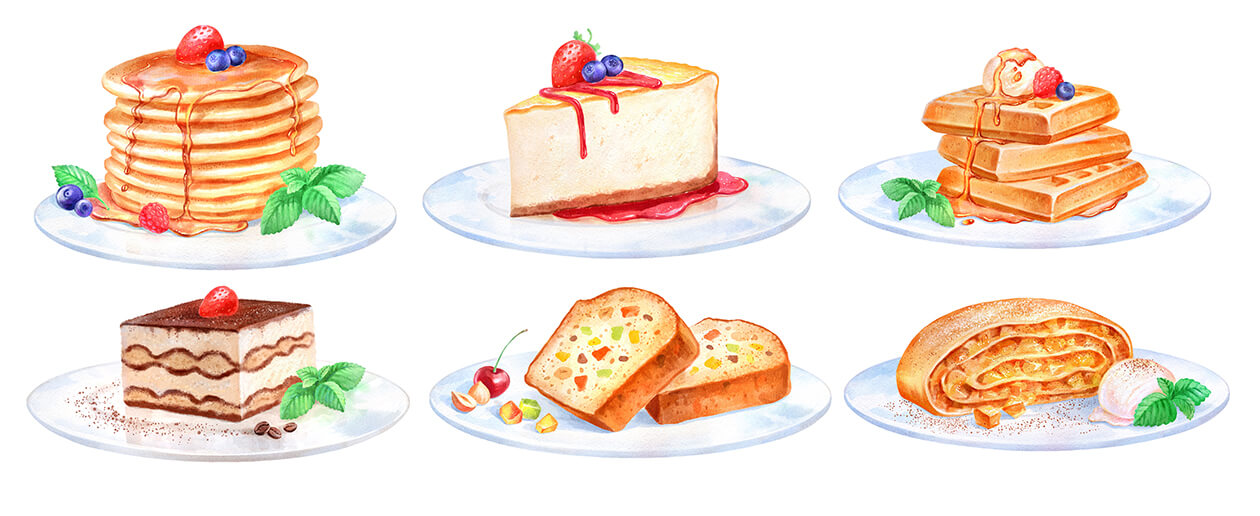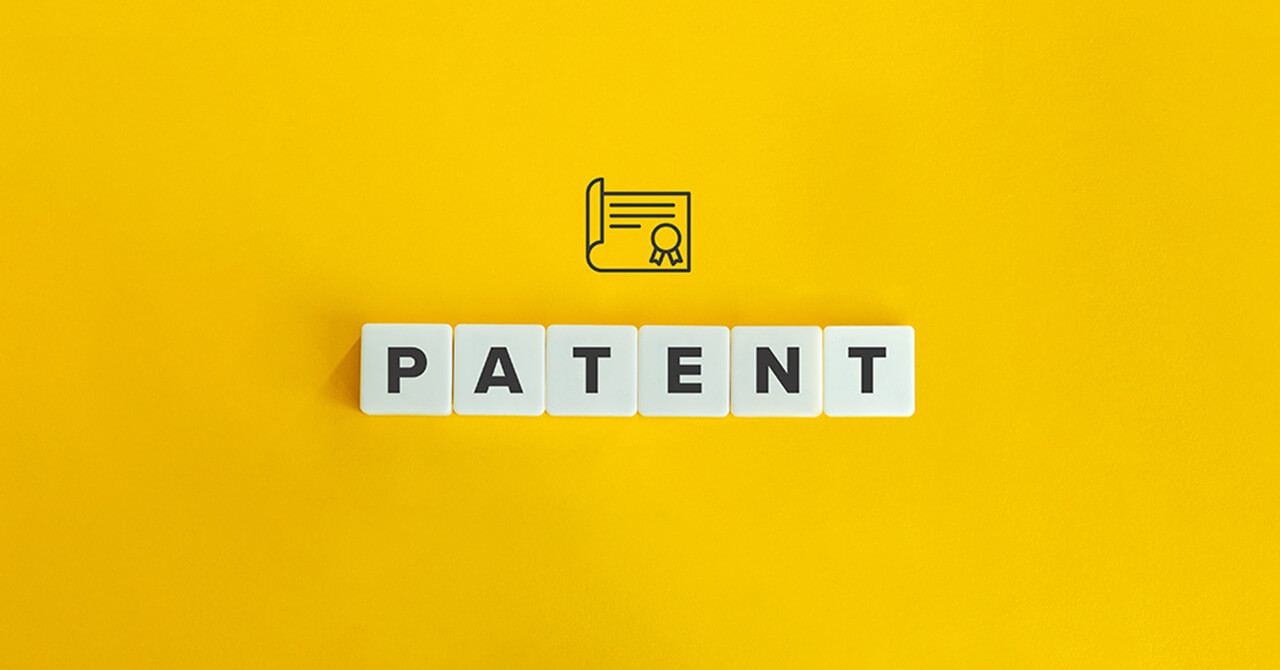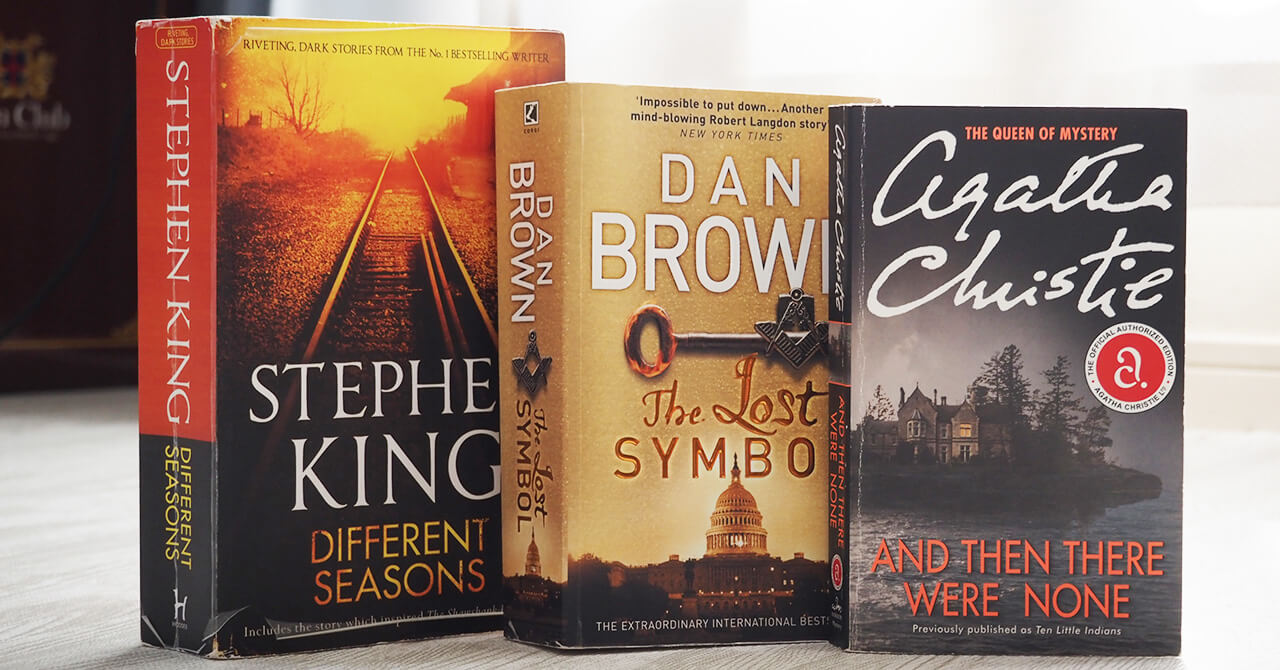- 2025.07.09
- スタッフブログ
【品質管理課ブログ】これまでとこれからについて

新卒でインターブックスに入社して以来、多くの案件に関わるなかで、翻訳の品質管理に求められる視点や責任の重さを実感しながら経験を積んできました。
そこで、今回のブログでは、これまでの歩みを振り返りつつ、日々の業務で感じていることを書いてみようと思います。翻訳会社に興味を持っている若い世代の方々の参考になれば幸いです。
なぜ翻訳会社へ?
まずは、翻訳会社に入社するまでを振り返ってみます。
翻訳に携わる方々に共通することかもしれませんが、昔から言葉に関心を持っていました。小学生のころは漢字が好きで、中学生から高校生までの間は英語などの外国語が好きでした。大学では、文学や言語学を学ぶよりも、他の分野について学んで視野を広げたいと思い、以前から興味を持っていた法学部に進学しました。同級生の多くは公務員志望でしたので、わたしもその影響を受け、卒業後は法律に関わる仕事に就くだろうと思っていました。
翻訳という仕事を意識したきっかけは、ゼミナール活動でした。わたしが所属していたゼミナールでは、特定のテーマについて、概要、判例、学説、私見をゼミ生がレジュメと答案に書きまとめ、それらをたたき台として議論しつつ、書きまとめた文章を添削する活動を行っていました。指導教官からは、助詞を適切に用いること、文は一読して理解できるように書くこと、一文には一意を込めることなど、文章作成のコツを学びました。条文や判例を読み込んで議論することも楽しかったですが、他のゼミ生が書いた文章を添削しているうちに、日本語そのものに関心が向くようになりました。例えば、「は」と「が」の違い、品詞のはたらき、熟語の意味、読みやすい文章の特徴などについて考えることがおもしろかったのです。次第に、卒業後は言葉と向き合う仕事がしたいという思いが強くなりました。日本語も英語も好きで、じっくりと言葉と向き合うことが性に合っていたので、翻訳に興味を持ち、翻訳学校に通うことを決めました。このときは大学4年で、多くの同級生は就職活動を終えていたので、不安もありましたが、悔いが残らない道を選ぼうと思い、進学しました。
翻訳学校では、実務、出版、映像の翻訳について学びました。同じ志を持つ方々と言葉について深く語り合える環境のなかで、非常に充実した1年を過ごすことができました。社会人経験がありませんでしたので、まずは会社に入って経験を積むことが必要だと考え、縁あってインターブックスにチェッカーとして入社しました。
翻訳の現場で培った視点
インターブックスでは、さまざまな分野の翻訳に対応しています。このため、チェック作業においては、多様な分野の文書に接してきました。不慣れな分野の文書をチェックすることもありましたので、調査が非常に重要で、常に知識をアップデートする必要がありました。
特に、特許翻訳においては、制度や法令に関わる知識に加え、発明の技術的背景を理解する力が求められます。機械や化学などの専門分野に関わる内容が多く、正確な理解のためには事前の調査と知識の蓄積が欠かせませんでした。また、出願方法によって訳出の仕方が異なったり、形式面での決まりごとがあったり、初出と既出を区別したりするなど、留意すべき点が多々ありましたが、インターネットや書籍を駆使して調べつつ、周りのみなさんのお力をお借りして、ひとつひとつ対応してきました。特許分野の文章は、法律のような堅い文章であったので、法律を学んだ経験が活かせたようにも思います。
一方、商品説明文や観光向けの文書などの翻訳においては、原文に忠実な訳文よりも、読者のこころに響く訳文のほうが好まれ、意訳が求められることがありました。原文の意図を正確にとらえつつ、印象に残る訳文にすることが重要な分野です。文脈やわかりやすさを考慮して、あえて原文どおりに訳さない場合もあり、翻訳の奥深さを感じました。一口に翻訳といっても、特許翻訳のように一言一句を正確に訳すタイプもあれば、商品説明文などの翻訳のように、原文の意図を抽出して魅力的に伝えるように訳すタイプもあり、実に多様です。どのように翻訳が使用されるか、どのような読者を想定しているかなどに応じて、訳文のスタイルを柔軟に調整することが重要だと感じます。
これからの展望
これまでの業務を通じて実感したことが2つあります。
ひとつは、日本語と英語に関わる知識をアップデートしつつ、垣根を問わず知識を吸収していく必要があるということです。高品質の翻訳を実現するためには、原文を正しく理解して適切に翻訳する力を高めることも重要ですが、原文が属する分野の背景知識を得ておくことも不可欠です。単に字面を訳すのではなく、背景や文脈を考慮して、自然な訳文に仕上げることを心がけていきます。
もうひとつは、翻訳はリレーだということです。これまでは、ひとりで黙々と取り組む個人種目だと思っていましたが、翻訳者、チェッカー、プロジェクトマネージャーのみなさんがつなぐリレーだと思うようになりました。各自が役割を果たし、適切にバトンを受け渡すことによって、高品質の翻訳がつくりだされるのだと思っています。わたしも、バトンをしっかりと受け継いで、チェッカーの責務を全うし、次の走者につなげていきます。
さいごに
日々の業務を通じて、翻訳は非常にやりがいのある仕事だと感じました。もちろん、簡単な仕事ではなく、地道な調査や細かな調整が求められます。特に、固有名詞、周辺知識、ファクトチェックなどの調査には多くの時間がかかり、大変さを感じることもありますが、こうした作業を乗り越えた先に、高品質の翻訳があるのだと思います。高品質の翻訳をご提供するために、日々研鑽を積み、言葉に対するアンテナを大きく張って、これからも目の前の文と真摯に向き合っていきます。
 |
|
品質管理課メンバー:ルゴーサ 盛岡生まれの新米チェッカー。物心がついたときから鉄道ファンで、小学校の卒業文集には新幹線の運転士になりたいと書きました。高校の外国語科で英語を勉強した後、「リーガル・ハイ」の古美門研介や「HERO」の久利生公平に憧れて法学部に入学するも、法律学の森で迷子になる。卒業後、翻訳学校を経てインターブックスに入社。特許分野を勉強中。趣味は鉄道旅行。流れゆく車窓を眺めながら、鉄道車両(特に気動車)の走行音を聴くのが大好物です。次はどこに行こうかと常に考えています。
|
外国語対応でお困りですか? どうぞお気軽にお問い合わせください。
無料ご相談・お問い合わせフォーム関連記事