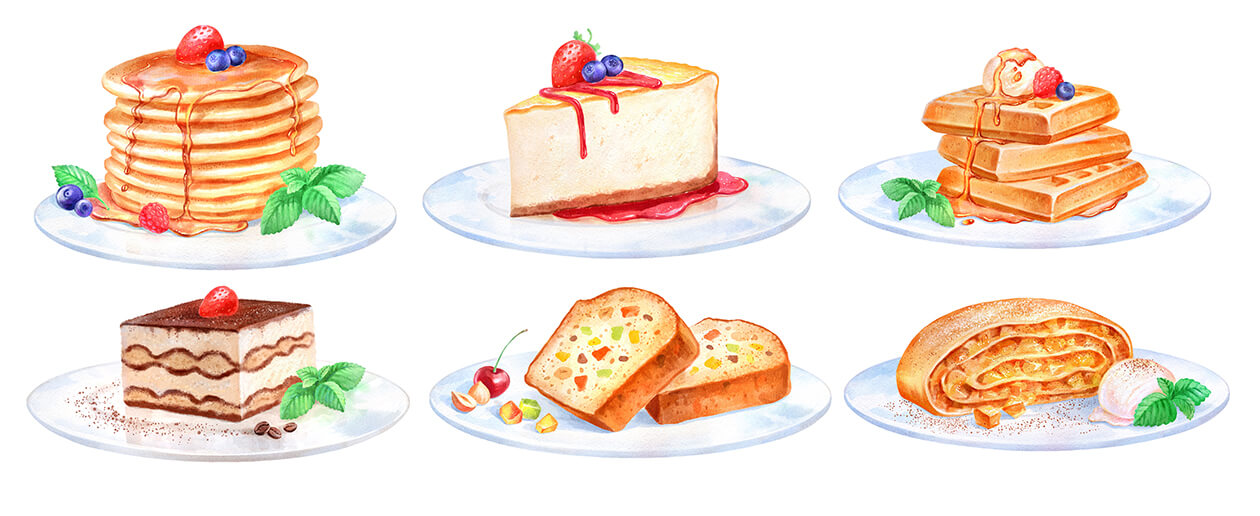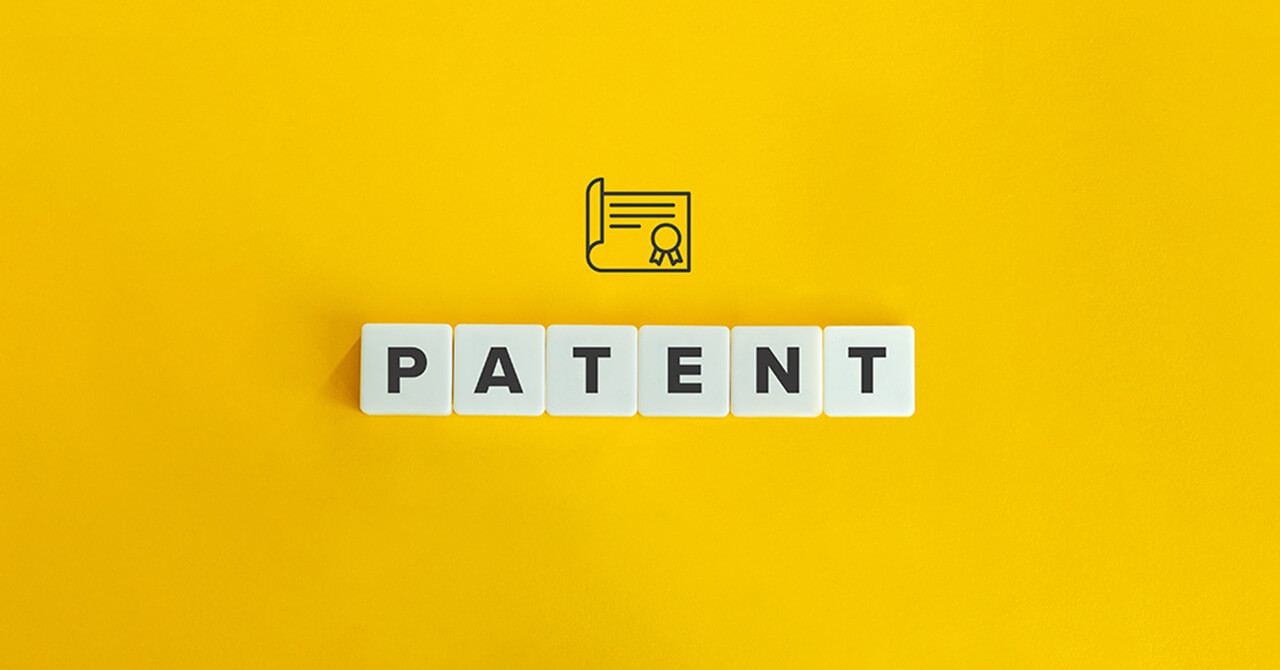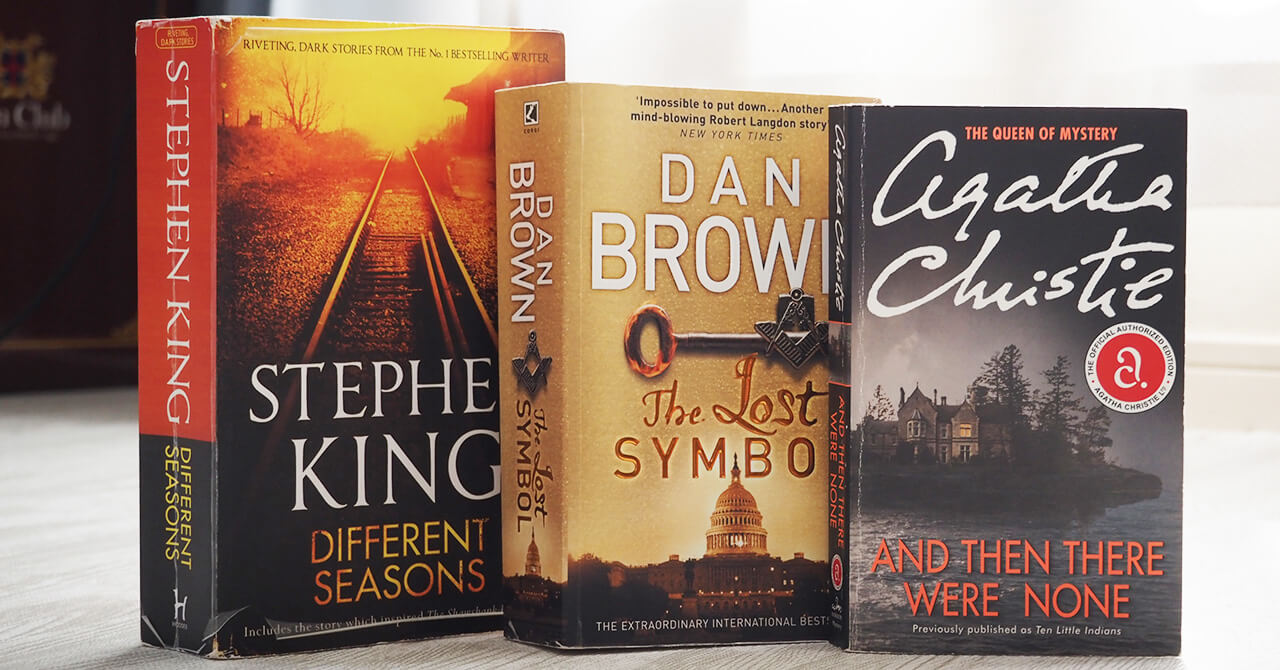- 2025.09.10
- スタッフブログ
【品質管理課ブログ】旅で覚えた英語たち

以前は旅行会社に勤めていて、海外ツアーの添乗に行く機会が多くありました。
現地に日本語を話せるガイドさんがいる場合、観光地などについての説明はガイドさんにお任せすればよいのですが、日本語を話せるガイドさんがいない場合、英語ガイドさんが話す内容を日本語に訳してお客様に案内するということも添乗員の仕事になります。
そんな添乗員の仕事の中で覚えた英語をいくつかご紹介したいと思います。観光にまつわる簡単な単語ばかりです。
添乗員が旅で覚えた英語
phosphate
北アフリカに位置するチュニジアは、世界でも有数のリン鉱石の産出国です。
レザールージュという名前の観光列車があり、渓谷の中を走るこの列車に乗ると、雄大な景色を楽しめます。そして、この列車が走る一帯は、リン鉱石の産地でもあります。
ツアーでこの列車に乗りに行くと、当然、ガイドさんが「ここはリン鉱石(phosphate rock)の産地だ」と説明してきます。
当時、化学物質の英語名には全く馴染みがありませんでしたが、ここで「phosphate(リン酸塩)」という単語を覚えました。
stork
日本ではほとんど見かける機会のない「コウノトリ」です。ヨーロッパなどで、電柱や屋根の上に大きな巣を作っているコウノトリを何度か見かけました。
またチュニジアでの話になりますが、首都のチュニスからブラレジアというローマ遺跡に行く途中にベジャという町があり、いくつもの電柱の上に巣を作っていたコウノトリが印象に残っています。
簡単な英単語ではありますが、普段の生活で実際に使うことはないので、旅先で出会った英語として心に残っているものの一つです。
kingfisher
これも鳥の名前です。「カワセミ」です。どこかの国で鳥を見かけて、「あれはkingfisherだよ」とガイドさんに教えてもらったことがあるような気もしますが、kingfisherといえば、インドのビールを思い出します。
インドにも様々なビールの銘柄がありますが、一番有名なのが「キングフィッシャー」。ビールの瓶のラベルや缶には、「KINGFISHER」という文字とともにカワセミが描かれています。
このビールの会社が親会社だったキングフィッシャー航空という航空会社も、かつてインドにありました。
carob
イナゴマメってご存知でしょうか?私は地中海に浮かぶ島キプロスに行った際、ガイドさんにイナゴマメの木を見せてもらい知りました。英語では「carob」。地中海地域を原産とするマメ科の木です。
イナゴマメは食物繊維が多く、便秘にいいそうです。そして、種子の重さが均一であるとされたため、古代には天秤の分銅として用いられ、宝石の重さを表す単位の「カラット(=0.2g)」はイナゴマメのギリシャ語名「キャラティオン」に由来するといわれているそうです。
この話を聞いた時は、へぇ~、そうなんだ!と思ったのを今もよく覚えています。莢に糖分を多く含み、甘味料や家畜の飼料として用いられ、近年ではチョコレートの代替品として注目されています。
種子には、粘性のある多糖類「ローカストビーンガム」が含まれていて、ソースのとろみ付けやゼリーの凝固剤など食品添加物として世界中で広く利用されていますが、日本では食品ラベルに「増粘多糖類」として一括表示されるので、イナゴマメの名称を一般的に目にする機会はあまりないそうです。
heather
続けてまた植物の話になります。ヒース(heath)といえばご存知の方も多いかもしれません。エミリー・ブロンテの小説「嵐が丘」の舞台となったのが、ヒースという植物が茂る荒野。
「ヒース」とは本来「荒野、荒地」を意味し、そこに群生するのが「ヘザー(heather)」と呼ばれる植物です。
北イングランドやスコットランドなどでは夏の終わりに赤紫色の花をつけ、荒涼たる大地を彩ります。日本ではエリカと呼ばれることもありますが、エリカはツツジ科エリカ属の総称で、ヘザーはエリカ属に含まれます。
北ドイツには、エリカの花を楽しめるエリカ街道というのもあります。
宗教関連の用語
自然にかかわる英単語の話ばかりになってしまいましたが、当時かなり覚えたのが宗教関連の英語でした。
ツアーでは、教会、モスク、寺院などが観光に入っていることが多く、覚えなければいけない英語が山ほどありました。
例えば、イスラム教の礼拝堂モスクに行けば、minaret(尖塔)、mihrab(聖地メッカの方向を示す窪み)が必ずあります。
キリスト教の教会を訪れる場合は、聖書のエピソードを知っておく必要があり、悩ましいのが聖書の登場人物の日本語名と英語名が違う場合。洗礼者ヨハネはJohn the Baptist、ペテロはPeterなど、覚えることは尽きませんでした。
おわりに
今回ご紹介した英語は、ほとんどの場合、その場で聞いて覚えたわけではなく、訪れる場所について下調べをして予習をして覚えていった英語です。
海外ツアーの添乗員が現地の英語ガイドさんの話を聞いて、お客様に日本語で案内する仕事は、通訳の仕事に似ています。
プロフェッショナルな通訳者の足元にも及ばないレベルではありますが、通訳の技量が足りなければ足りないほど、ツアーで訪れる国のことについて調べておくという準備が大切です。
どんなに高い英語力や日本語力があったとしても、その国のことについてよく知らないと、その場で話を聞いただけではうまく説明できないと思います。
現在は品質管理課の一員として、日英・英日翻訳のチェックを行っておりますが、やはり調べるということが重要だと思います。
原文の分野や内容に合った訳文を完成させるには、原文の内容について調査したり、訳文では適切な用語が使われているか、用語の使い方が正しいかなどを調べたりすることが不可欠です。
翻訳のチェック業務を行う中で、何かを調べる時間というのがかなりの割合を占めており、旅行業界でのスピーキング力やリスニング力が試される仕事から、翻訳業界での文書に携わる仕事に変わっても、調べるという地道な作業は続いています。
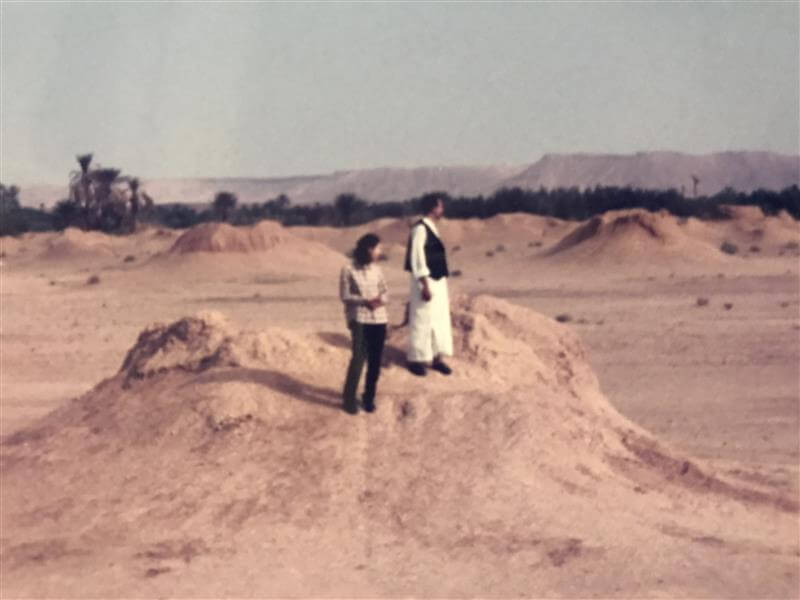 |
|
品質管理課メンバー:satikov 旅行会社に勤務後、PMとしてインターブックスに入社し特許分野を担当。その後、現在は特許翻訳のチェック業務をメインに行っています。旅行会社勤務時代はツアーの添乗業務もあったうえ、休みの日にも旅行に行っていたので、ほとんど家にいませんでした。今は完全デスクワークとなり、コロナで在宅勤務も行うようになって、すっかりインドアの生活を送っています。
|
外国語対応でお困りですか? どうぞお気軽にお問い合わせください。
無料ご相談・お問い合わせフォーム関連記事