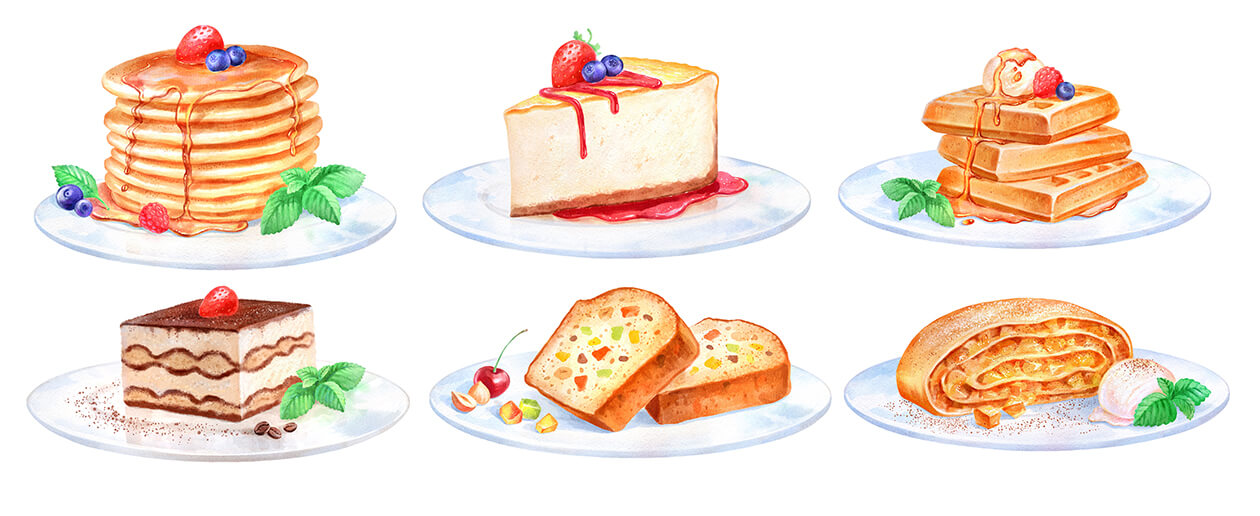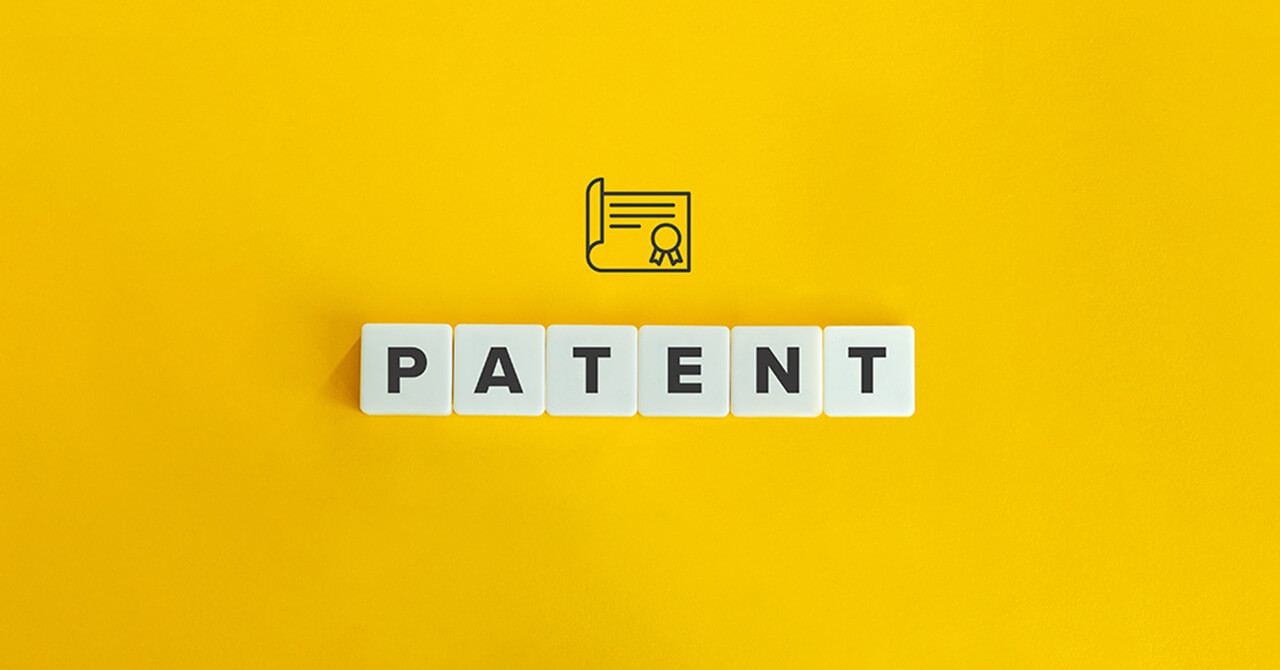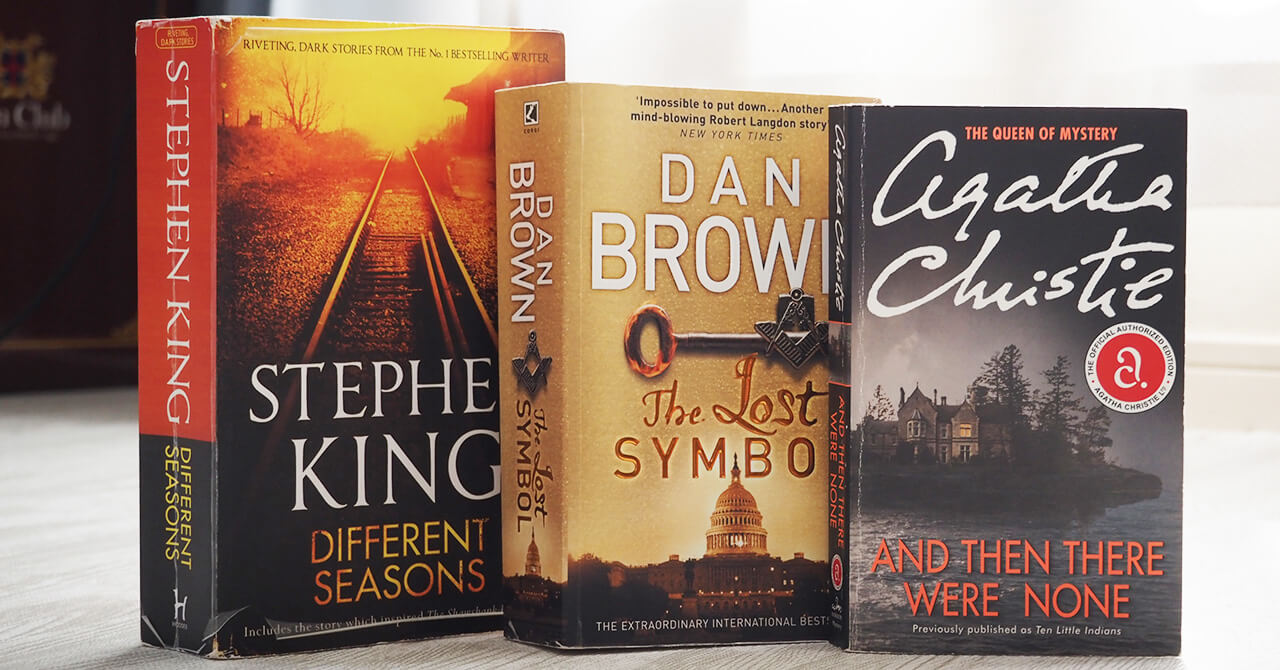- 2025.08.13
- スタッフブログ
【品質管理課ブログ】生成AIを翻訳チェックに活かす

生成AIの進化は翻訳業務にも大きな変化をもたらしています。IR文書の和英チェックを行う筆者も、その精度と利便性を実感しつつ、誤訳や解釈の揺れといった限界も痛感。AIの提案を参考にしながらも、自らの判断と裏付けを欠かさず、補助的ツールとして賢く活用する重要性を探ります。
AIが職を奪う?
最近、ウォール・ストリート・ジャーナルで気になる記事を見つけた。2025年7月2日付オンライン版で「CEOたちがついに本音を語り始めた~AIは仕事を奪う~」というものだ。
約850語という短い記事だったので、試しに某生成AI(以下、「当AI」)に日本語訳をさせて、翻訳チェッカーである私がおおまかに確認してみたところ、全体的な翻訳精度は非常に高く、特に気になるほどの明らかな誤訳や不自然な表現は見当たらなかった。
ただし、チェッカー目線から細かいことを言うと、訳抜け、意味があいまい、翻訳というより要約になっている、意訳しすぎているといった問題点がいくつか見られたのだが、翻訳対象となる文章の文字数、内容、ジャンル、専門性、難易度等様々な要因によってAI翻訳の精度は変わってくるのだろうとは思う。
チェック業務での使用
私は、大前提として情報流出がないように細心の注意をしながらではあるが、興味本位もあって、業務中に何か知りたいことがあるたびに当AIに質問をしている。あくまで翻訳チェックでの使用に条件を限定しての話だが、当AIに対する現時点での私の評価はある程度固まっている。「参考にはできる。だが鵜呑みにしてはいけない」といったところである。あくまで補助的に、賢く利用すべきだと考えている。
なお、私は企業IR文書(決算短信、決算説明会資料、株主総会招集通知、有価証券報告書、統合報告書等)の和→英チェックを担当することが多いので、以下では主に同分野でのチェック作業について記述している。
翻訳者が作成した訳文に訳抜け、誤訳(原文解釈間違い、係り受け間違い、固有名詞の正式表記の不使用を含む)があった場合に加えて、間違いとは言えないまでも不自然な表現や冗長な言い回しがあった場合などに訳文を修正する。納期に追われながら自分で適切な訳を考え出すよりは時間短縮・効率化になるかと思い当AIの回答を参考にすることも多い。
特に、そもそも日本語には存在しない概念(例えば、名詞の可算・不可算および単数形・複数形、冠詞など)や微妙な文法・語法の間違いなどは正否の判断が難しく、訳文を読んでいてなんとなく違和感を覚えるときには当AIが役に立つ。以前は社内のネイティブチェッカーに質問して教えてもらうことも多かったが、手を煩わせてもいけないので、最近は質問を控えめにして代わりに当AIに教えてもらっている。
後述するが、その回答内容が正しいかどうかを自分で確認・判断することを怠ってはいけないのは言うまでもない。なお、以下で紹介する原文は元の文書から抜粋の上、一部改変しており、対応する生成訳も調整している。
当AIが有効な具体例
以下では私が最近、当AIを使用した中での成功事例を述べる。
【原文の不備】
原文:東京都千代田区9丁目9-9 九段北タワー(原文を改変したため架空の住所および建物名を記載している)
当AI訳文:Kudankita Tower, 9-9-9 Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo
原文では「千代田区9丁目」となっているが、「千代田区九段北9丁目」が正しい表記のはずである。当AIが、実在する建物の所在地を確認した上で訳しているのかどうか定かではないが、正しく補って書かれているので感心した。ただし、どんな不備であっても当AIが補ってくれるというわけではないと思う。
【誤訳修正】
翻訳者の訳文が何となく変だと感じたときに、辞書で確認しつつ、当AIにも質問してみた。
例①
原文:コンプライアンス委員会では、取締役会より諮問を受けた事項に関し協議を行い、
誤訳:The Compliance Committee deliberates on matters consulted by the Board of Directors …
ここで、「consult」という動詞は「~に意見を聞く・相談する」いう意味での用法としては「consult (人)」、「consult (人) about (こと)」、「consult with (人) about/on (こと)」などの用法が一般的である。
上記和英を当AIにチェックしてもらったところ、「The Compliance Committee deliberates on matters on which it is consulted by the Board of Directors」など、文法的に正しい訳文を複数提案してくれた。
例②
原文:当社の電池は現在までに多くの自動車に搭載されており、
誤訳:The Company’s batteries have been equipped in many vehicles …
この文章も「equip」の用法が間違っていることを当AIが指摘してくれた。「Many vehicles have been equipped with the Company’s batteries」とか、「The Company’s batteries have been installed in many vehicles」等である。
例③
原文:年次有給休暇取得率
誤訳:Percentage of employees taking annual paid leave
「従業員のうち年次有給休暇を取得した人の割合」という意味になっているが、正しくは、「従業員が付与された休暇日数のうち実際に取得した日数の割合」なので、
当AI英訳:Annual paid leave utilization rateなどが正しい。翻訳者の誤訳は、おそらく、直前に記載のあった
原文:男性労働者の育児休業取得率
英訳:Rate of male employees taking childcare leave
などに引っ張られたものと思われる。
【原文の重複表現】
IR文書では重複表現が多くみられるが、以下の文章では当AIは適切に対応している。ただし、これもすべての重複表現において有効かどうかは分からない。
原文:また、新卒採用計画は、人事部により各事業年度に新卒採用計画が策定され、取締役会による承認を受け確定します。
当AI英訳:In addition, the new graduate recruitment plan is formulated by the Human Resources Department for each fiscal year and finalized upon approval by the Board of Directors.
【自分では見落としていた誤訳】
当AIの効用として、自分にとって予想外の返答を受け取ることもある。例えば、チェック時に「宇宙機」の訳が「spacecrafts」になっていたのを見落としそうになったが、当AIに単複同形だとエラーを指摘されたため「spacecraft」に修正した。
【番外編(英語学習)】
業務中以外でも、英字新聞を読んでいて、うまく文意をつかめない場合は、スマホやタブレットで当AIの画面に該当箇所を貼り付けて、説明してもらう。知らない単語・フレーズに遭遇した時は辞書で調べるのだが、そもそも文章構造が見抜けない場合、口語表現やイディオムが含まれている場合、背景知識がないと意味が分からない場合など、独力では解決できない問題に対して示唆に富んだ知見を与えてくれるので非常に助かっている。
文章中にジョーク、ユーモア、皮肉が含まれていることに自分では気付かなかったのだが、当AIに教わって納得することもある。
当AIの生成訳をそのままでは使えない場合の具体例
当AIの回答には間違いもあるので注意が必要だ。実際、チャット画面の一番下には「当AIは間違えることがあるので、重要な情報は確認してください」との免責文の記載がある。日本語原文の言いたいことは分かるもののやや言葉足らずな場合や、係り受けの関係が不明瞭だったり表現があいまいだったりして複数の解釈が可能な場合など、当AIで誤訳になった例を以下に挙げる。
例①
原文:気候変動課題に関する協議、策定、実行を担う
当AI誤訳:… responsible for discussing, formulating, and implementing climate change-related issues
原文では「~に関する」とあるので「課題を協議し、解決のための施策を策定、実行する」という意味なのだろうと読者が推測できるため文章が成立している。しかし上記英訳だと、「課題を協議、策定、実行する」となっており、「課題を策定、実行する」というのは意味が通じない。当AIに指摘したところ、適切な答えが返ってきた。
例②
原文:第四次中期経営計画をビジョン2025で掲げた変革に取り組むための準備期間と位置づけ、
当AI誤訳:We position the Fourth Medium-Term Management Plan as a preparatory period for driving transformation set forth in Vision 2025, …
しかし、「計画(plan)」を「期間(period)」と位置づけるという表現は厳密には正しくないので当AIに指摘したところ修正訳を示してくれた。その内容も適切だった。
例③
原文:パリ協定の目標に準拠して、世界平均気温の上昇を産業革命前比で2℃未満に抑えるシナリオと現状を上回る対策をとらず4℃の温暖化が進むシナリオを採用し、
当AI誤訳:In line with the goals of the Paris Agreement, the Group has adopted two scenarios: one in which the rise in global average temperature is limited to 2°C above pre-industrial levels, and another in which no additional measures are taken, resulting in a 4°C increase in global warming.
係り受け間違いである。「パリ協定の目標に準拠して、」は「2℃未満に抑える」に係る。パリ協定では「世界共通の長期目標として2℃目標の設定、1.5℃に抑える努力を追求すること」を定めている。しかし、英訳では「2つのシナリオを採用した」に係っているため、4℃のシナリオも含んだ訳となっている。
例④
原文:人身傷害、物的損害や労働災害、竣工後の苦情による多額の補修費用
当AI誤訳:… substantial repair costs arising from personal injury, property damage, work-related accidents, or post-completion complaints, …
人身傷害からも補修費を負担するという英訳になっている。
生成AIとの付き合い方を考える
当AIの返答に対して納得がいかずに再度、こちらから疑問点を指摘するのはよくあることだ。すると可愛げがあることに、謝罪して別の回答を提示してくる。過ちを素直に認める姿勢は評価できるが、あまり頻度が高くなるとユーザーの側としては当AIの言っていることの何が正しいのか、そうでないのか、分からなくなってくる。
また、以前与えた質問と同じ質問をしても異なる回答が返ってくることがある。2つの時点の間に行ったやり取りを当AIが学習しているのだろうと思う。普段の当AI使用時にはあくまで文書の一部を断片的に翻訳させているため、文書全体を翻訳にかけたならば結果が異なってくるだろうとも思う。日本語原文を英訳用に再構成した後に、当AIで翻訳をすれば精度は上がってくるだろうが、事前作業の負担が大きくなり、コストもかかることになる。
結局のところ、生成されたテキストの内容を自分で吟味し、裏取りをし、判断をするということが重要になってくるのだろう。分からないことに出くわしたらウェブ上の信頼のおけそうな情報源を丁寧に調べるなど、普段から真摯に業務に取り組んで、少しでもそのような判断力を磨いていきたい。
なお、ここで書いた内容はあくまでも2025年7月時点におけるものであり、今後のAIの進歩により現時点での課題が解決されていくことも多いのかなとも思う。
 |
|
品質管理課メンバー:Tall Bridge Hero(日⇔英翻訳チェッカー) 学生時代に会計学、経済学を学び、卒業後は経理の職に就くなど、紆余曲折を経て現在に至る。翻訳業界ではかなり遅咲きなので日々新たな発見をすることが多いが、かつて学んだ知識を今の仕事に活かせているという安心感と、これまで積み重ねてきた翻訳チェックの経験により、少しずつ仕事面での自信が芽生えてきた。今後も謙虚に学ぶ姿勢を大切にしていきたい。
|
外国語対応でお困りですか? どうぞお気軽にお問い合わせください。
無料ご相談・お問い合わせフォーム関連記事